【半導体】インテル(INTC)は事業分割するべき?クレイグ・バレット元CEOは事業分割案に反対?
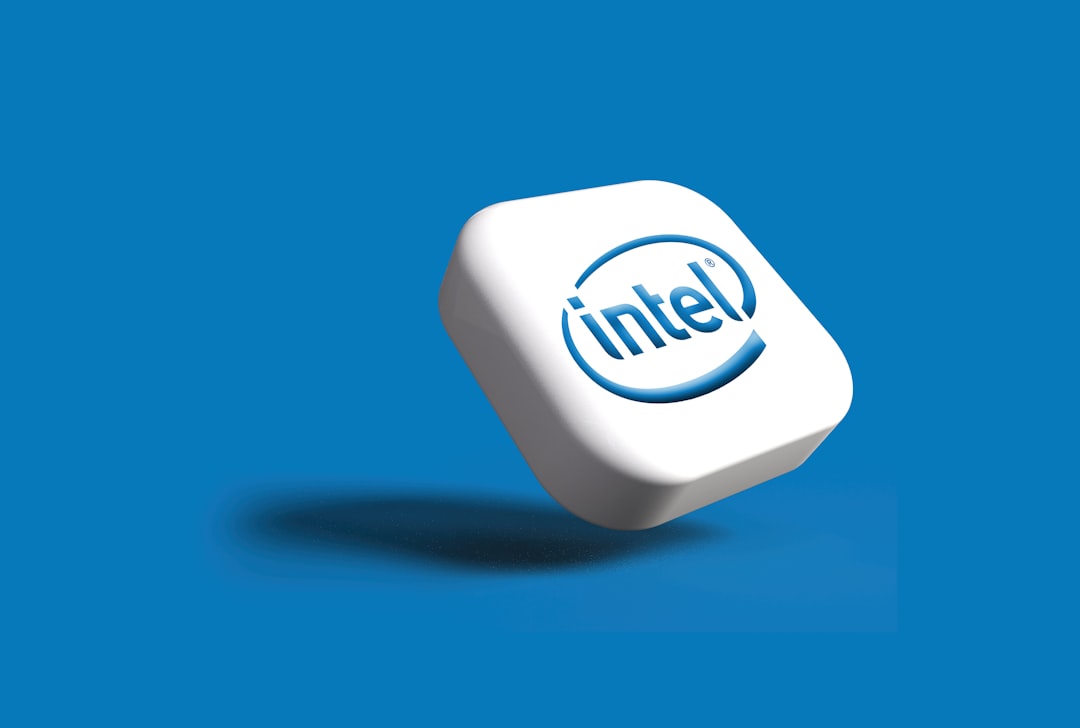
 ウィリアム・ キーティング
ウィリアム・ キーティング- 本稿では、足元でよく耳にする「インテル(INTC)は事業分割するべき?」という疑問に答えるべく、クレイグ・バレット元CEOによる直近の事業分割案に対する見解の詳細な分析を通じて、私の見解、並びに、今後のインテルの見通しを詳しく解説していきます。
- インテルの元CEOであるクレイグ・バレット氏は、インテルの分割案に反対し、同社の技術力の向上を強調しました。しかし、彼の主張には希望的観測が含まれており、実際の競争優位性には疑問が残ります。
- インテルのエンジニアがLinkedInに投稿した技術進捗に関する記事が削除され、同氏のプロフィールも消えたことが話題になっています。これはインテルの慎重な情報開示方針と関係があると考えられます。
- インテルはオハイオ州の旗艦工場の建設を5年延期することを発表しました。これにより、経営戦略の見直しが必要とされる中、同社の財務状況やリーダーシップに対する懸念が高まっています。
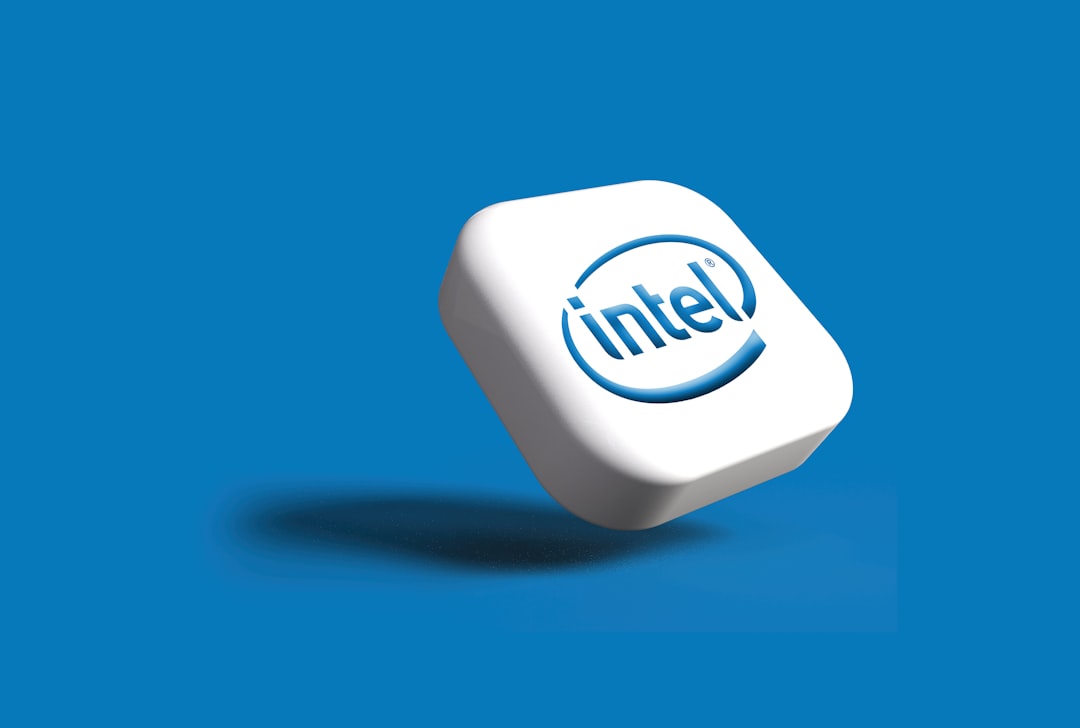
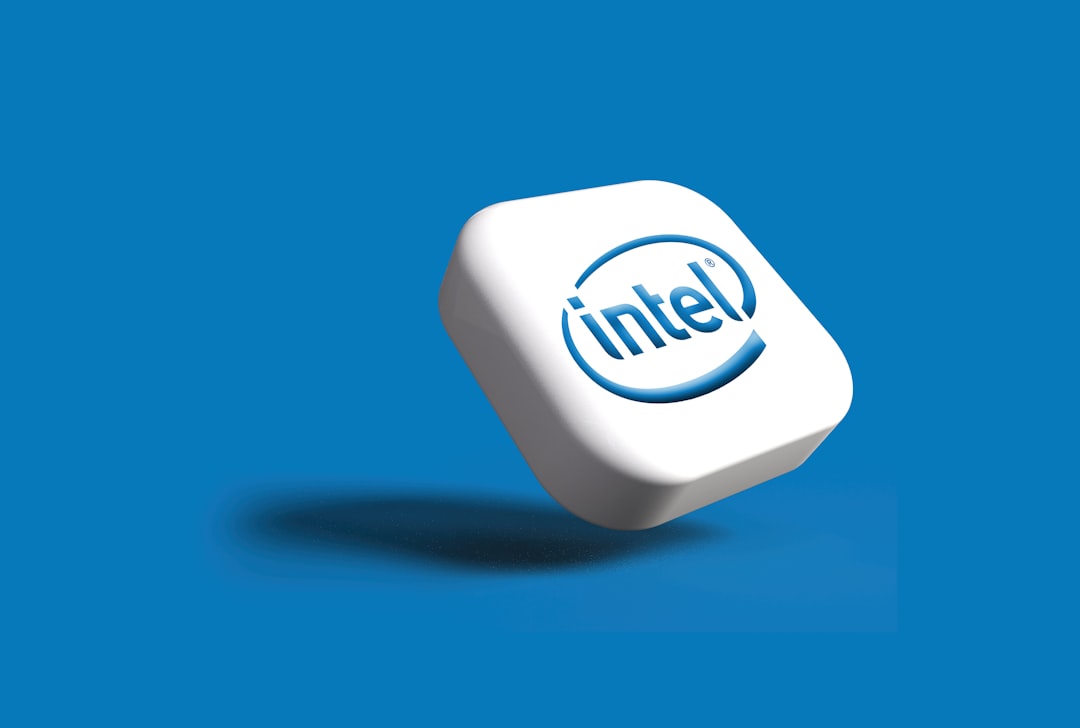
 ウィリアム・ キーティング
ウィリアム・ キーティング