シスコ・システムズ(CSCO):サイバーセキュリティ銘柄のテクノロジー上の強み(優位性)&競合分析と今後の見通し・将来性
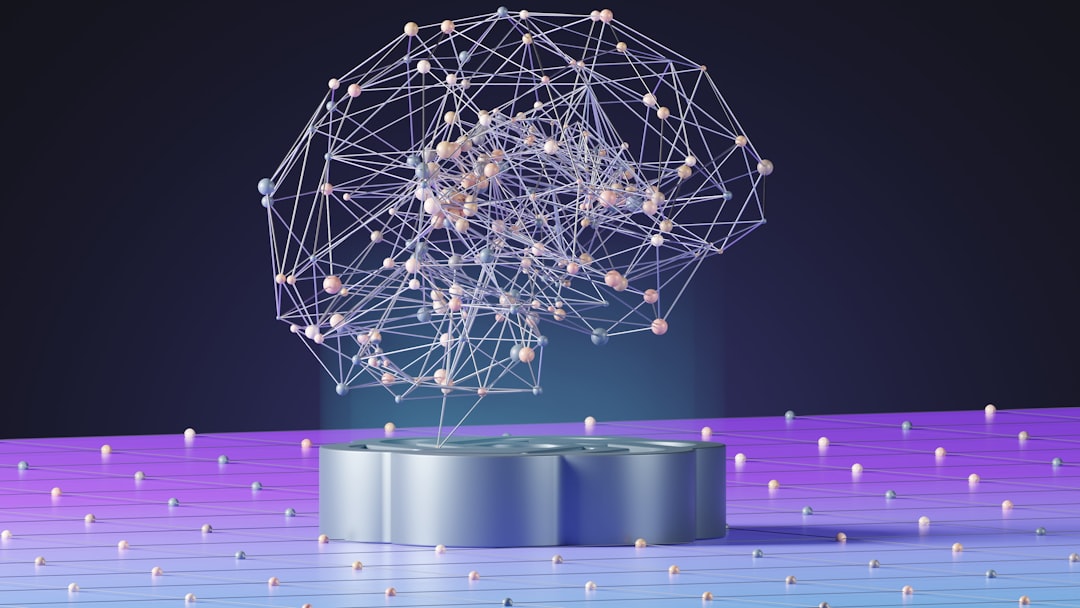
 コンヴェクィティ
コンヴェクィティ - シスコ・システムズ(CSCO)はレガシー・テックの巨人として課題に直面しており、近年は技術革新や買収で苦戦している。
- 同社は、優秀な人材を獲得するためにOutshiftという社内ベンチャーを設立したり、新しいサイバーセキュリティ・ソリューションであるHypershieldを導入するなど、成長と評判を復活させるための努力をしている。
- Hypershieldは、eBPF技術とAIを活用し、企業のアプリケーションを保護するために設計された、分散型の自己進化型自動セグメンテーションおよび保護ソフトウェアである。マイクロサービスの課題を解決し、自動パッチ適用とポリシー制御を提供することを目的としている。
- Hypershieldは斬新なコンセプトであり、市場で受け入れられ採用されるには、同社が市場を啓蒙する必要がある。そして、同社がこの啓蒙を行うことができれば、Hypershieldはゲームチェンジャーとなる可能性を秘めていると見ている。
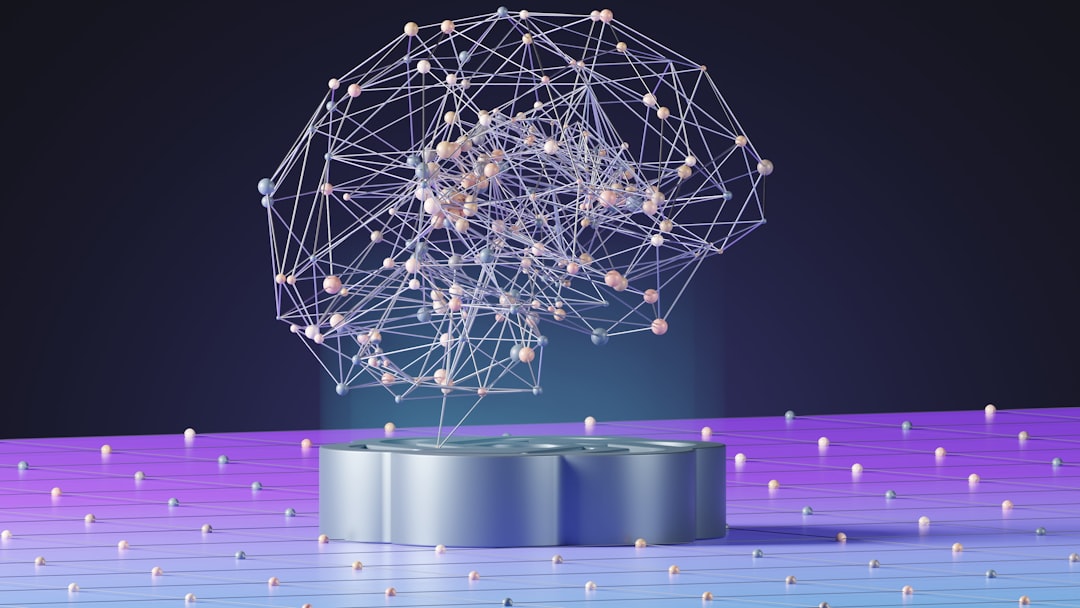
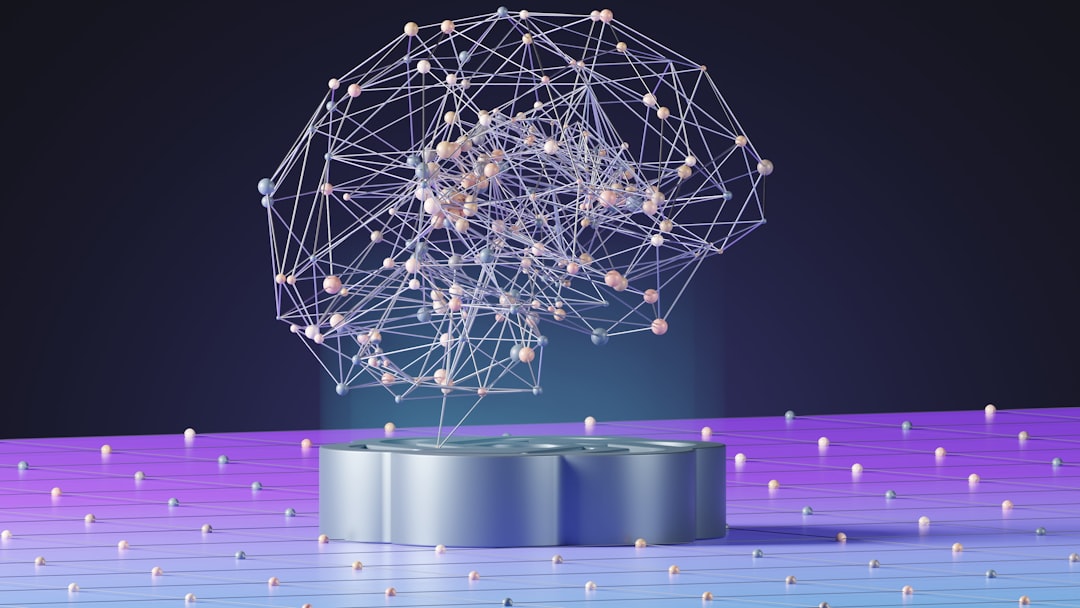
 コンヴェクィティ
コンヴェクィティ