インテル(INTC)は最大で20%の人員削減を実施!経営幹部チームの再編やリーダーシップ構造のフラット化にも邁進!
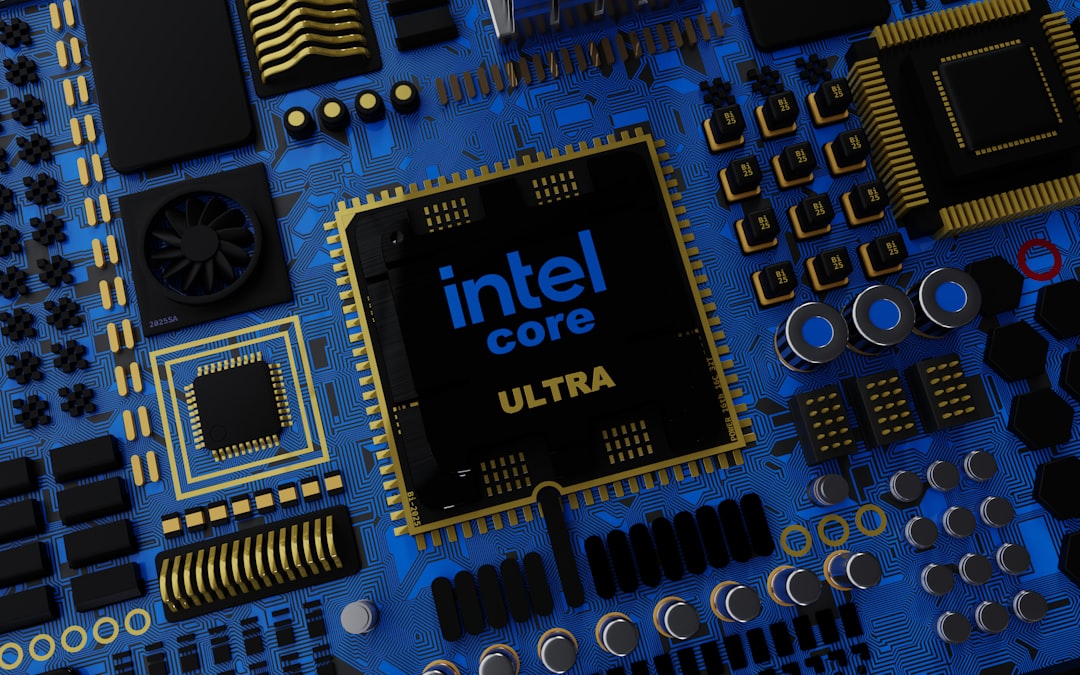
 ウィリアム・ キーティング
ウィリアム・ キーティング- 本稿では、注目の米国半導体銘柄であるインテル(INTC:Intel)の4月24日発表の最新の2025年度第1四半期決算分析を通じて、足元で発表された人員削減と経営幹部チーム(ELT)の再編に関して詳しく解説していきます。
- インテルでは、Lip Bu Tan(LBT)CEOのもとで経営幹部チームの再編やリーダーシップ構造のフラット化が進められ、複数の幹部が退任・昇格し、組織改革が本格化しています。
- インテルは最大20%の人員削減を計画しているものの、CHIPs法による補助金との兼ね合いから正式な規模や範囲の発表を避け、慎重な対応を取っています。
- LBT氏は出社義務の強化やOKR制度の見直しを通じて、インテルの企業文化改革に取り組んでおり、即効性はないものの着実な第一歩を踏み出しています。
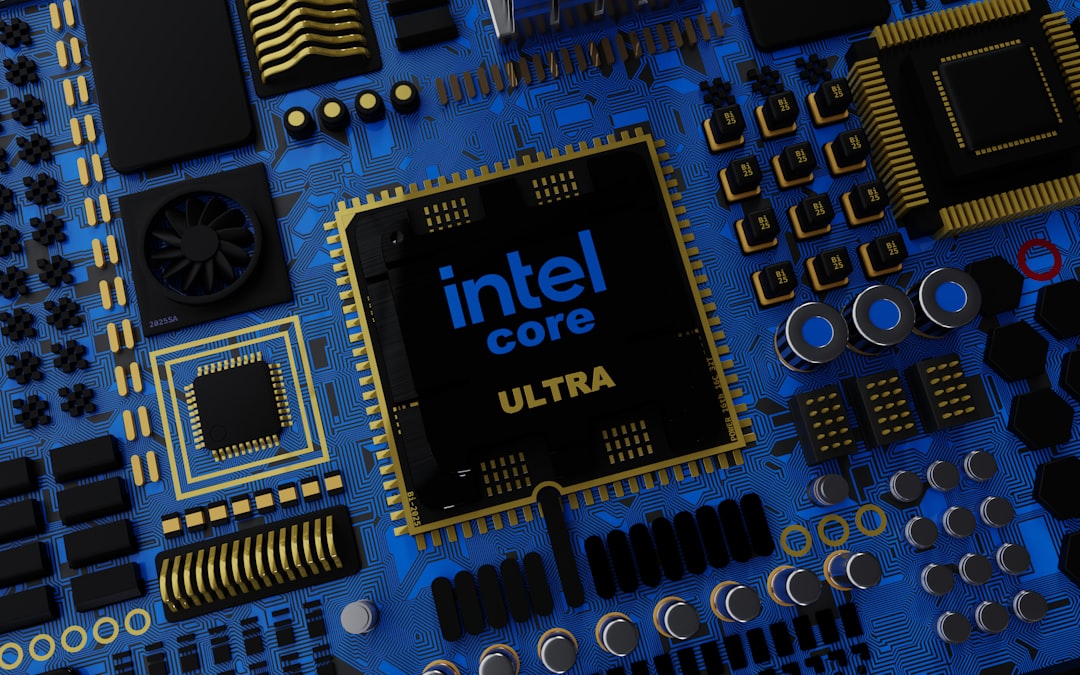
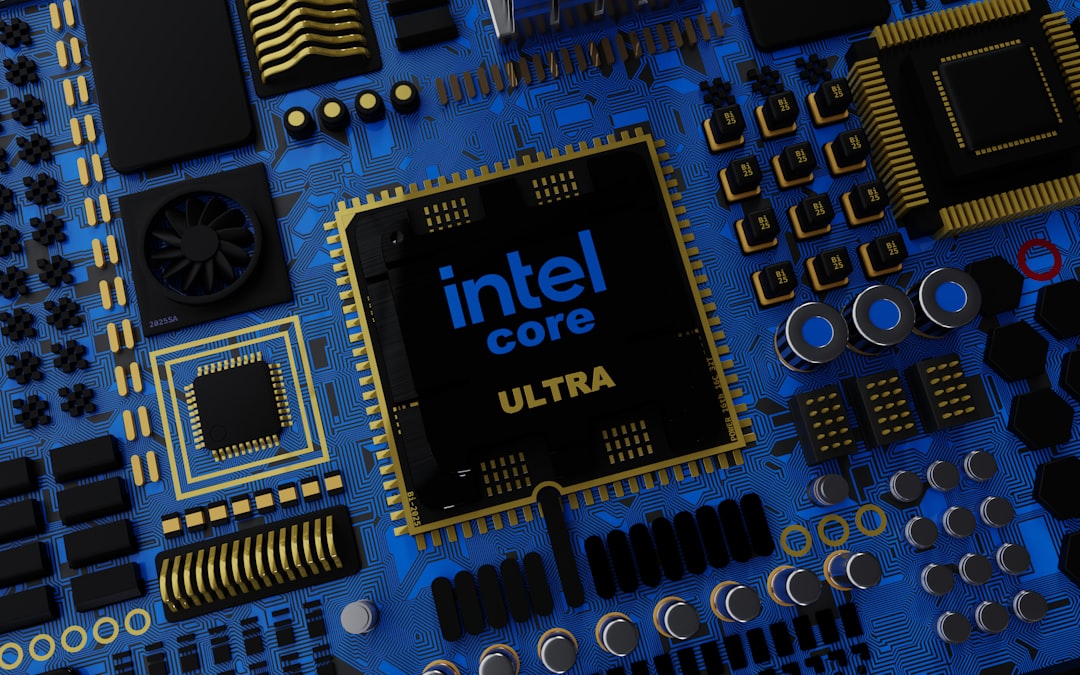
 ウィリアム・ キーティング
ウィリアム・ キーティング