【半導体:Part 3】トランジスタの進化とGAA(Gate All Around:ゲート・オール・アラウンド)の関係とは?
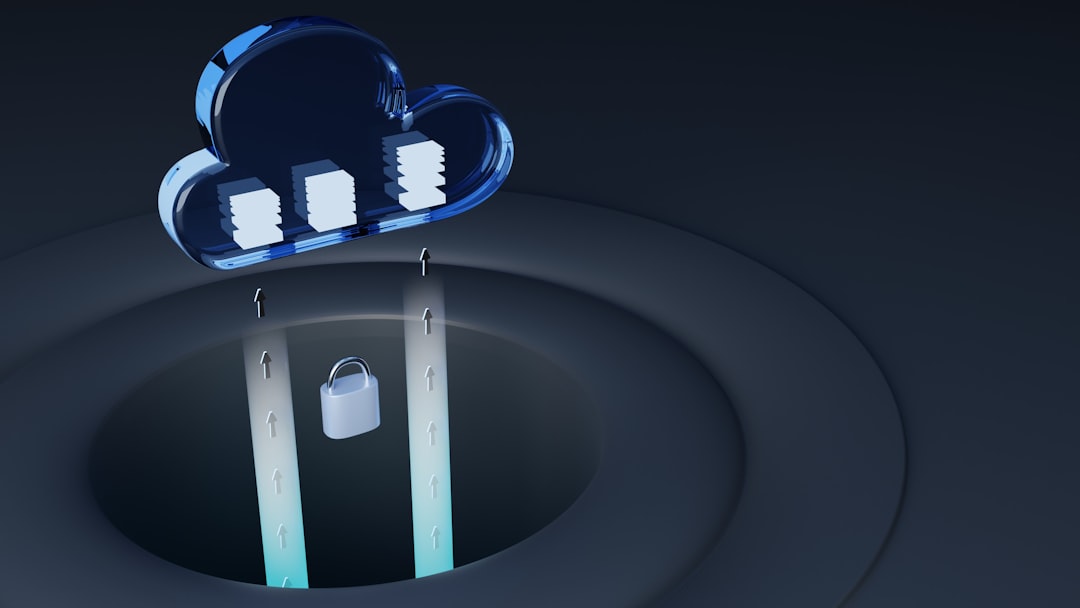
 ウィリアム・ キーティング
ウィリアム・ キーティング- 本編は、半導体市場における注目のテクノロジー、GAA(Gate All Around:ゲート・オール・アラウンド)の現状と将来性を詳細に分析した長編レポートとなり、4つの章で構成されています。
- 本稿Part 3では、半導体トランジスタの進化とGAA(Gate All Around:ゲート・オール・アラウンド)の関係を詳しく解説していきます。
- トランジスタ技術の進化は、過去70年にわたり革新を重ねながらも、基本的な製造プロセスやツールがほとんど変わらず維持されています。
- インテルが導入した「ストレインドシリコン」や「ハイKメタルゲート」などの技術革新は、業界標準となり、性能向上と微細化を可能にしてきました。
- 今後のGAA技術への移行が、トランジスタ設計において「進化」を超える「革命」をもたらすかが注目されています。
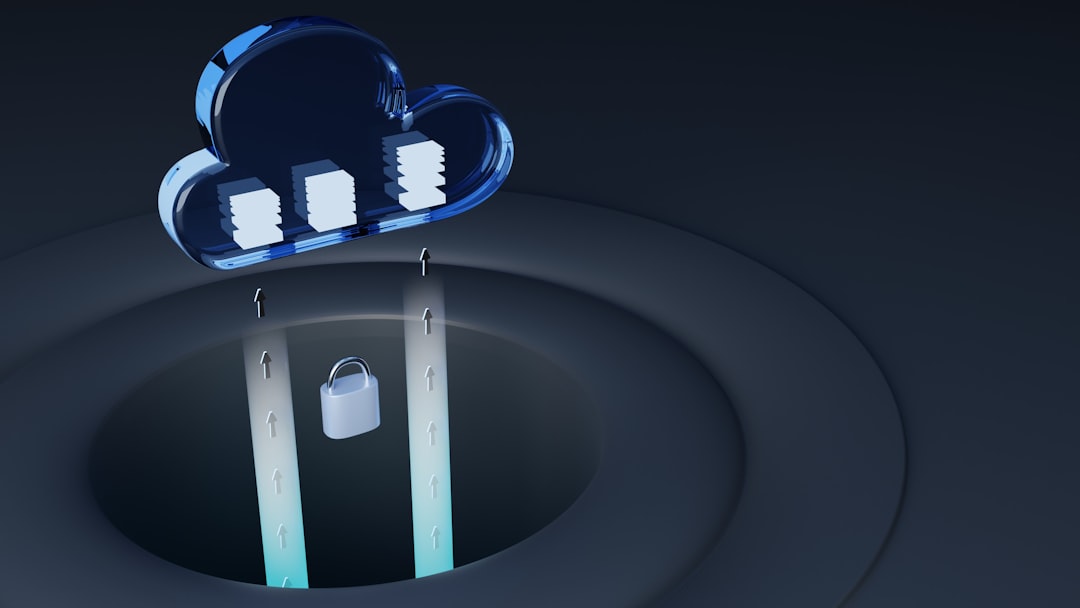
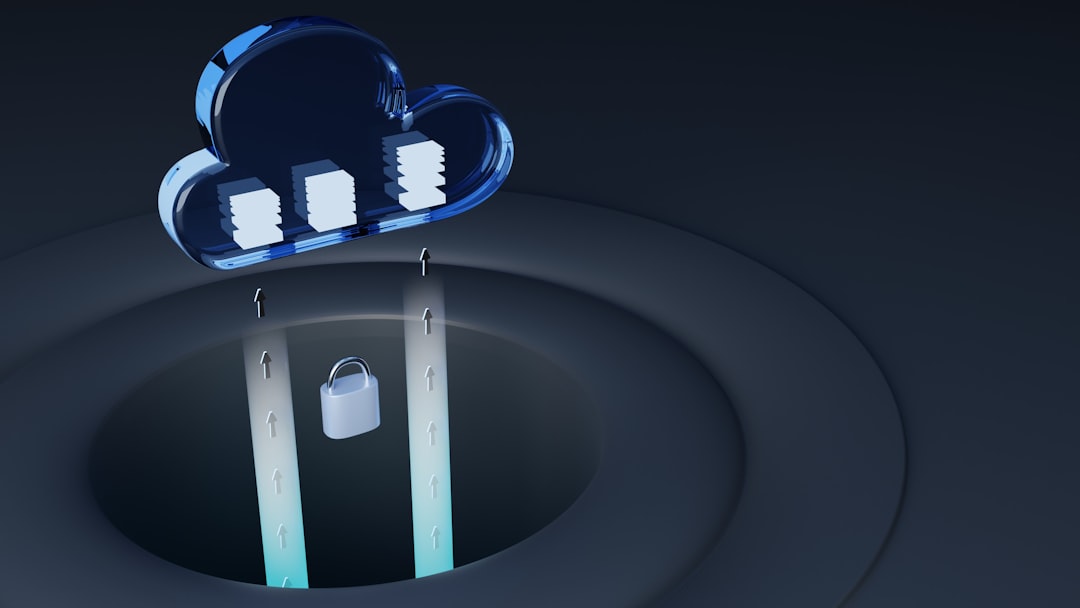
 ウィリアム・ キーティング
ウィリアム・ キーティング