【半導体】AIバブル崩壊はいつなのか?AI関連の半導体需要は減速傾向も、自動車関連は加速局面へ?
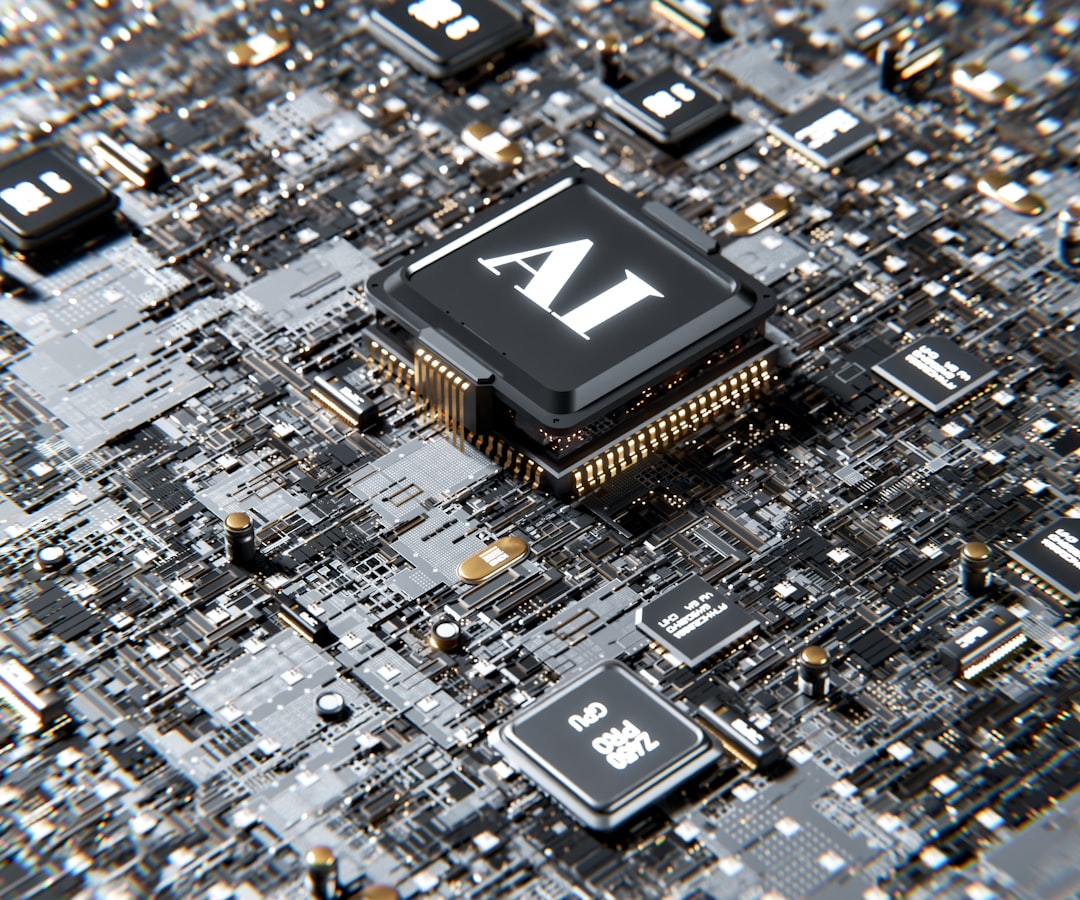
 ダグラス・ オローリン
ダグラス・ オローリン- 本稿では、「AIバブル崩壊はいつなのか?」という疑問に答えるべく、AI関連の半導体需要の詳細な分析を通じて、AI市場と半導体市場の今後の見通しを詳しく解説していきます。
- AI関連分野では供給過剰の兆しや資金源の制約が見られ、サイクルの終盤に差し掛かっている可能性がありますが、今後の景気動向には依然として不確実性が残っています。
- 一方、自動車分野ではEVを中心とした最終需要が回復しつつあり、在庫調整も進んでいることから、サイクルの反転と成長局面への移行が期待できるようにも見えます。
- 多くの投資家や企業がまだこの変化に気づいていない中で、割安に放置された半導体銘柄には再評価の余地があり、今後の注目分野となる可能性があります。
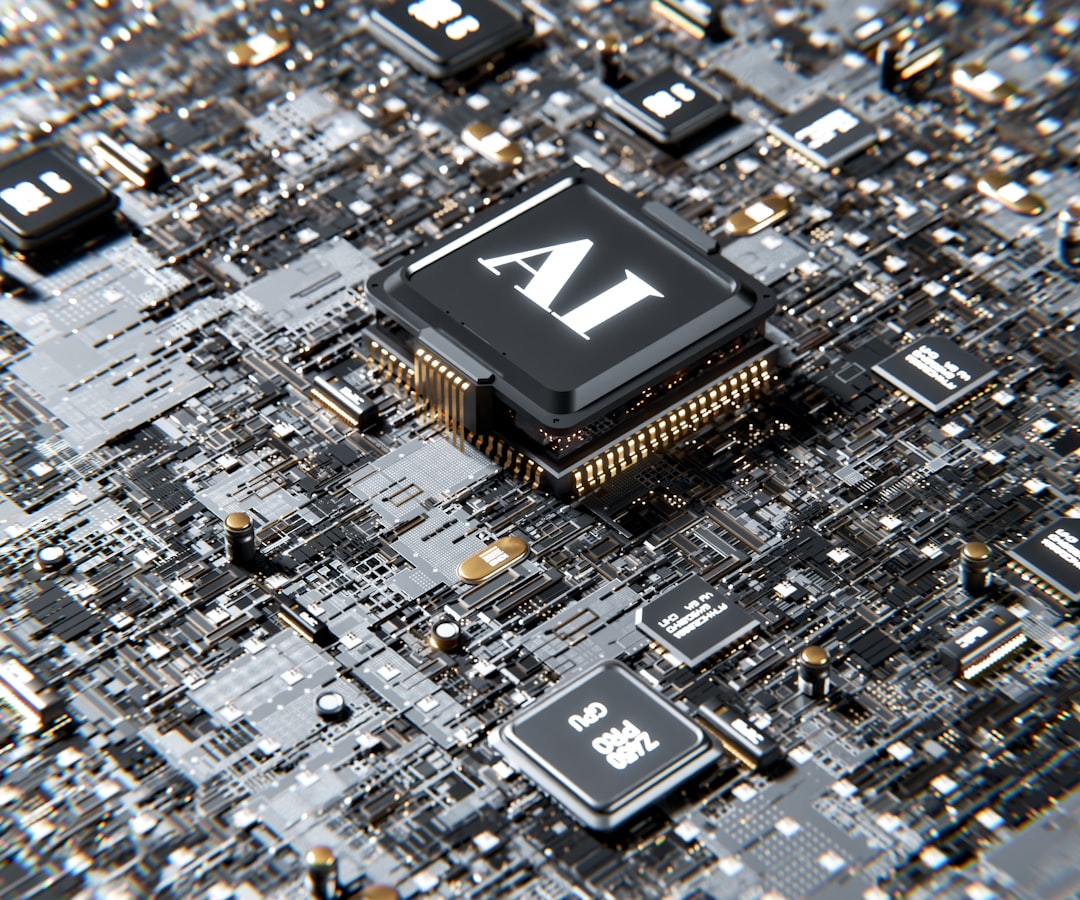
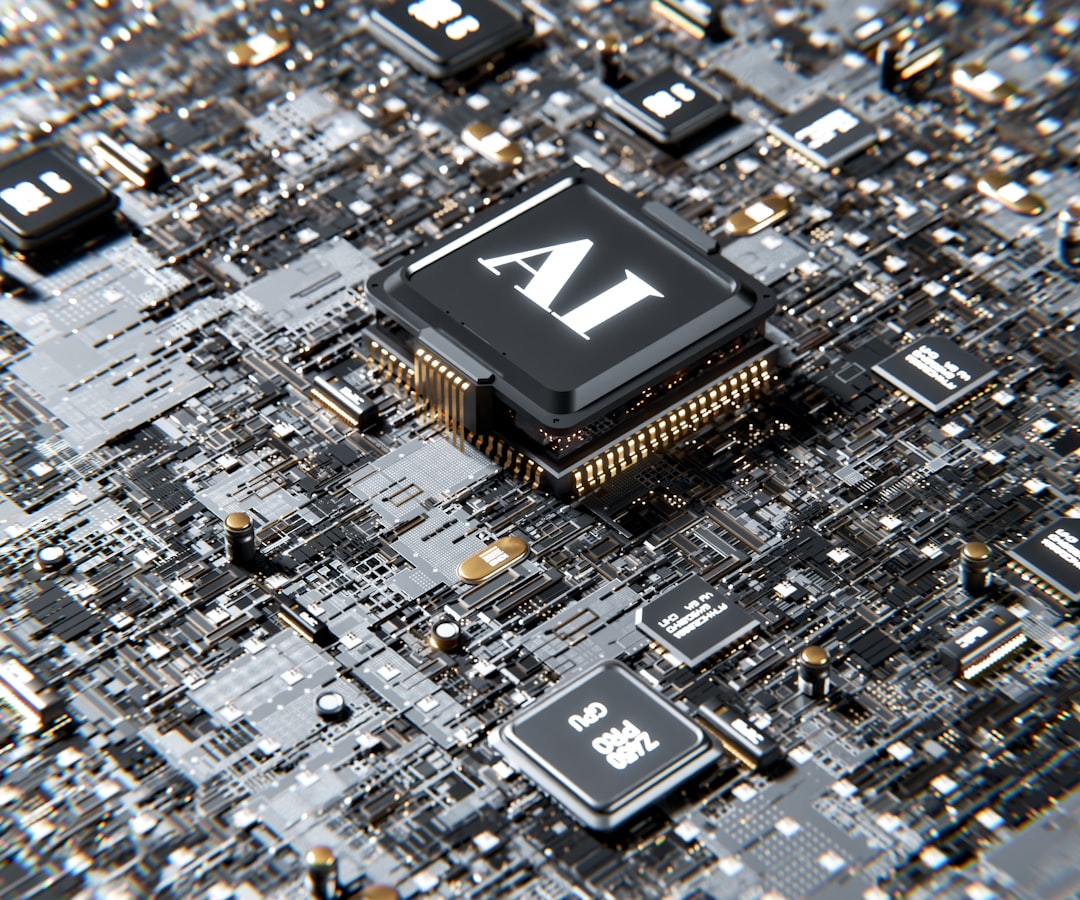
 ダグラス・ オローリン
ダグラス・ オローリン